「六曜?スピリチュアルじゃないの?」と思っていた過去の僕へ
社会人になるまで、「六曜(ろくよう)」なんて意識したことがなかった。
正直、「仏滅」とか「大安」とか聞いても、
「え、それっておまじない?スピリチュアル系の話?」
くらいに思っていた。
でも、社会人として何年か働くうちに、僕のその“なんとなくの無知”が、
ある日ガツンとぶつかることになる。
「それ、三隣亡(さんりんぼう)やで」——時が止まった瞬間
ある日、僕はお客さんとの打ち合わせで、
工事日程の提案をした。自信満々にこう言った。
「ここ、大安なので縁起もいいですし、この日でいかがでしょうか?」
そしたら、お客さんが一言。
「……それ、三隣亡やないか。あかんあかん。」
……は?
なにその技名みたいなやつ。
「サンリンボウ」って何!?!?!?
もう、恥ずかしさで顔が熱くなって、時が止まった。
「三隣亡」とは何者なのか?
調べてみて分かった。「三隣亡(さんりんぼう)」とは、
建築・工事関係の現場ではガチで避けられる要注意日だった。
この日に建築や増改築を始めると、
火事や不幸が起き、隣三軒まで災いが及ぶとされている。
こわ。
しかも、六曜とは別物だけど、カレンダー上は「大安+三隣亡」が重なる日もある。
だから「大安だからOK!」と単純に決めると、こういう地雷を踏むわけだ。
社会に出てから気づいた「六曜」は意外と根強い
六曜(ろくよう)とは、
結婚式、葬式、引越し、地鎮祭などの吉凶を判断する暦の一種。
「大安」「仏滅」「友引」など、縁起の良し悪しで使われる。
学生のころは意識しなくても、
営業・建築・冠婚葬祭系の業界では未だに超現役だということを、
僕は社会に出てから知った。
知らなかったら恥をかく?六曜の豆知識5選
そんな僕みたいな「知らなかった人」のために、
**“意外と知られていない六曜の豆知識”**を紹介しておく。
① 仏滅は、仏教と関係ない
「仏が滅ぶ」って書くから仏教由来っぽいけど、実は全く関係ない。
中国の占い「六壬(りくじん)」が元ネタ。
明治時代には一度、政府が「非科学的」として公式なカレンダーから外したことも。
② 赤口は「昼だけ吉」というクセあり日
基本的に凶日とされる赤口(しゃっこう)は、
11~13時(午の刻)だけ吉というややこしいルールがある。
この時間帯だけ「火の神様」が落ち着いているらしい。
③ 六曜を今も使うのは、ほぼ日本だけ
中国や韓国、台湾ではほとんど使われていない。
日本特有の“縁起文化”として今も根強く生き残っているのが六曜なんです。
④ 仏滅婚、実は“コスパ重視”で人気がある
最近は「仏滅プラン」で結婚式が安くなるケースも多い。
縁起よりも、実利で動く人も増えている時代。
「仏滅婚」=不吉、というイメージは、少しずつ変わってきている。
⑤ 大安でも安心できない日がある=三隣亡
はい、冒頭の僕のエピソード再来。
「大安だからOK」と思ってると、
三隣亡という爆弾が隠れているかもしれない。
特に建築業界では要チェック。
まとめ|知らない=恥じゃない。でも、学ばない=恥だ
社会人になってから、知ってて当然だと思われていることが
実は全然知らなかった——そんな経験、誰でもあると思う。
六曜や三隣亡もそのひとつ。
知らなかったことを恥じる必要はない。
でも、知ろうとしないことは、少し恥ずかしいかもしれない。
「知らないことは恥ではない。学ばないことこそが恥だ。」
——ソクラテス
今日この記事を読んで、「へぇ~」って思ってくれたなら、
あなたはすでにひとつ、“社会人としての知識”をアップデートしてる。
恥をかいてもいい。
それを、次に活かせば、それはもう“武器”になる。


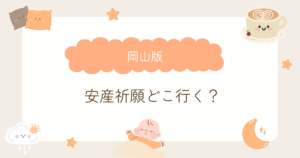
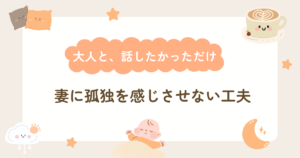



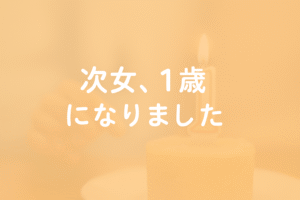
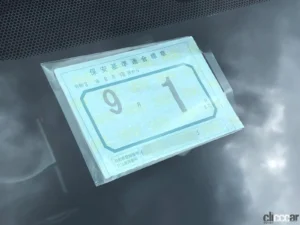
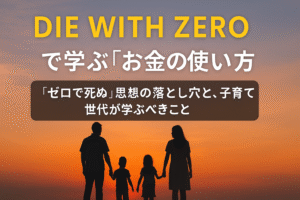



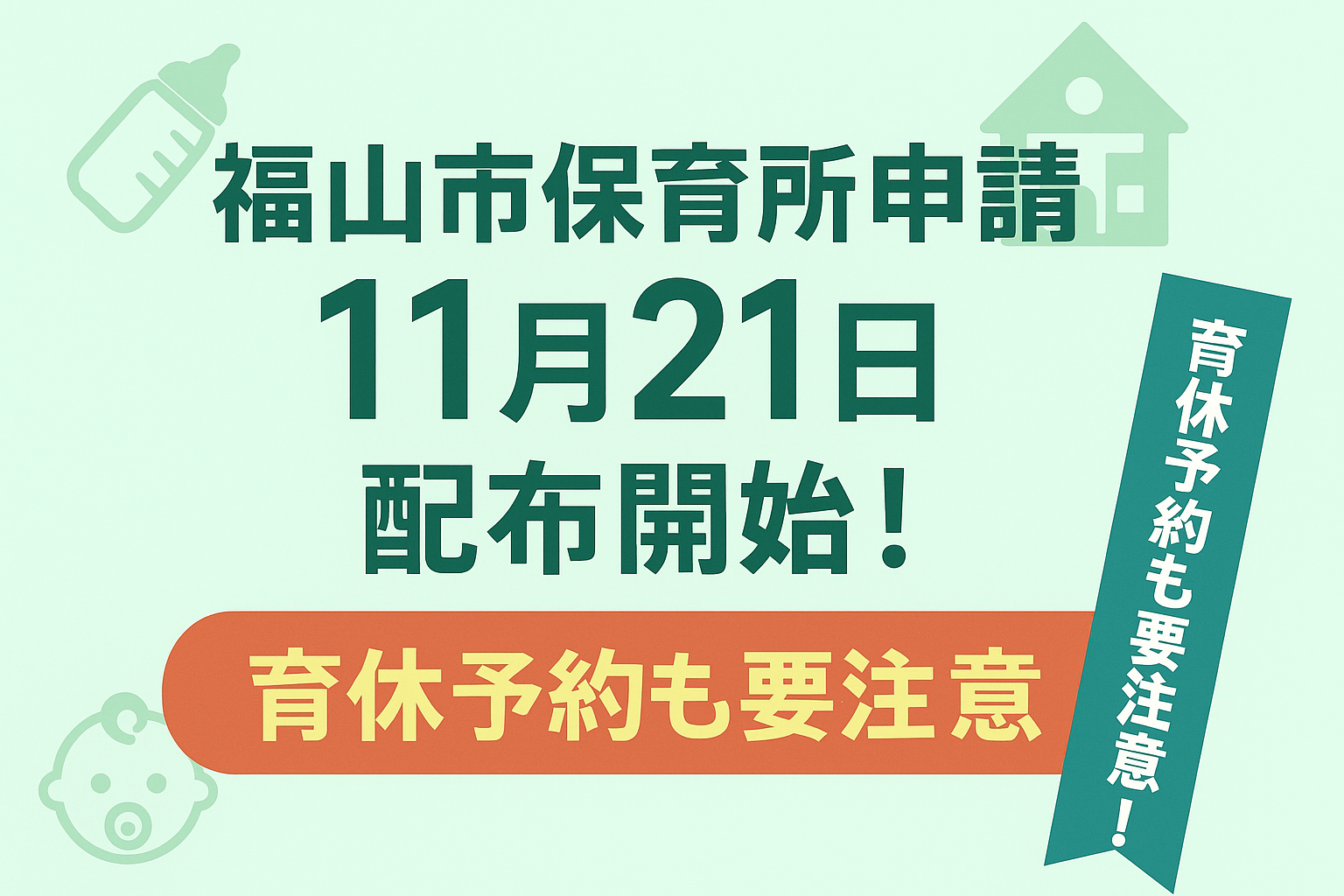
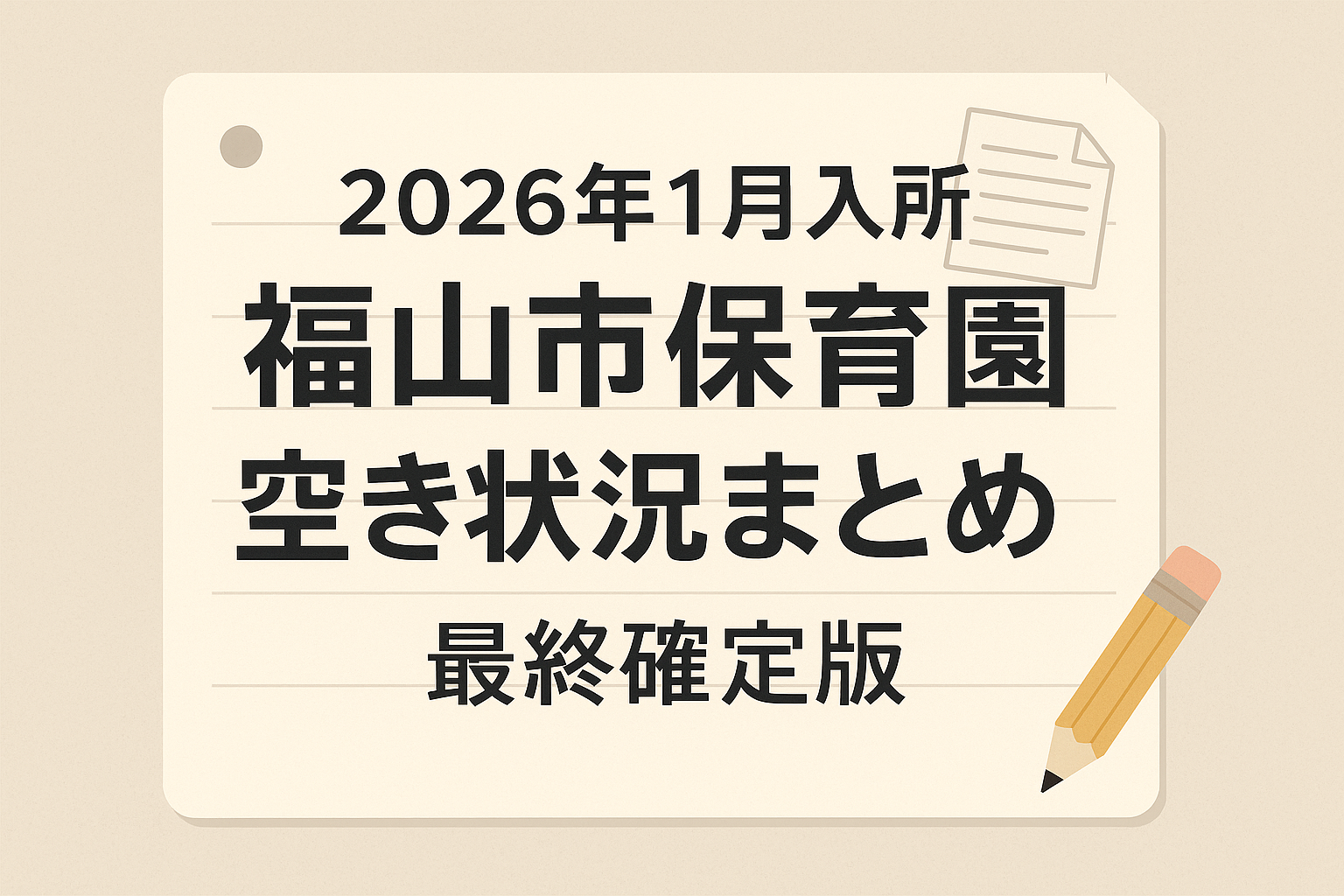
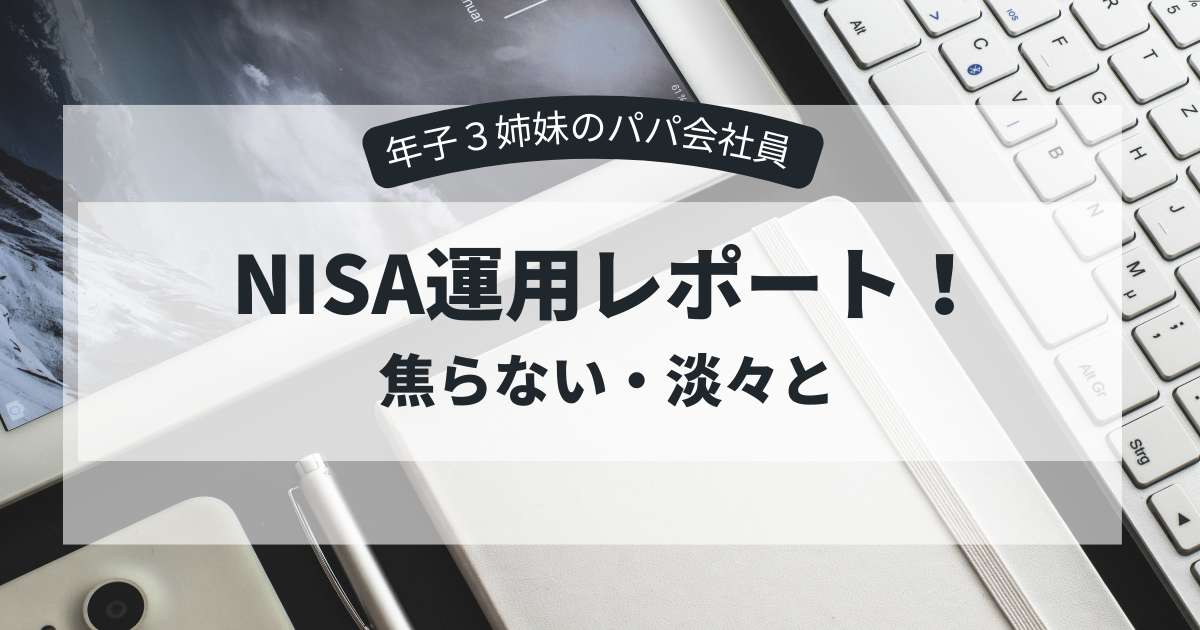
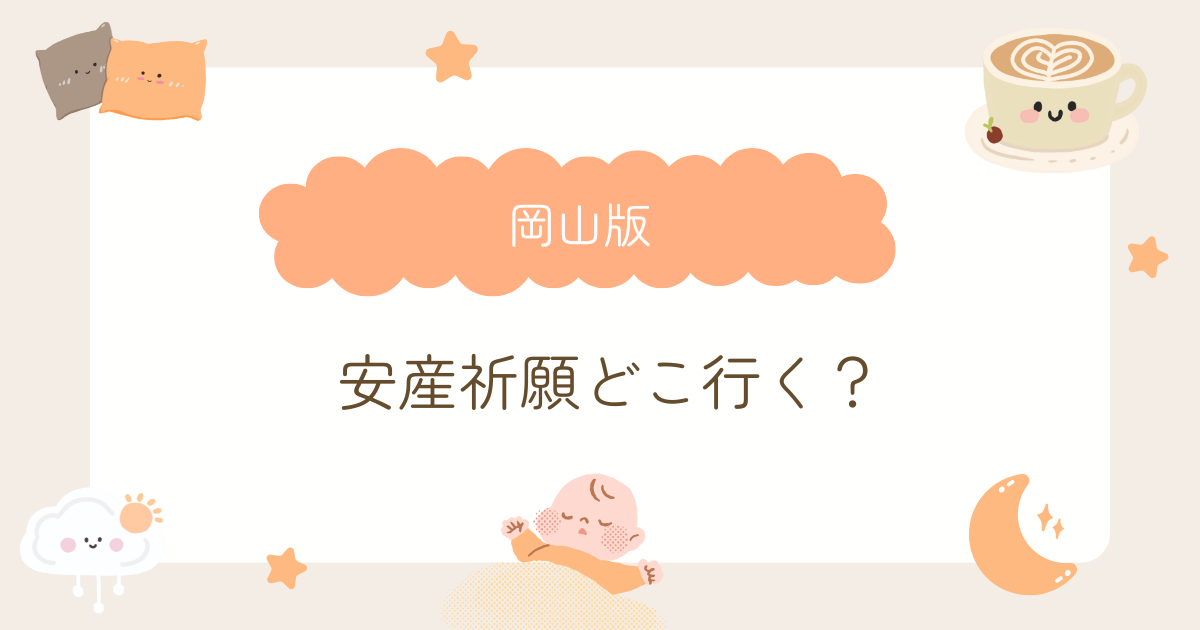
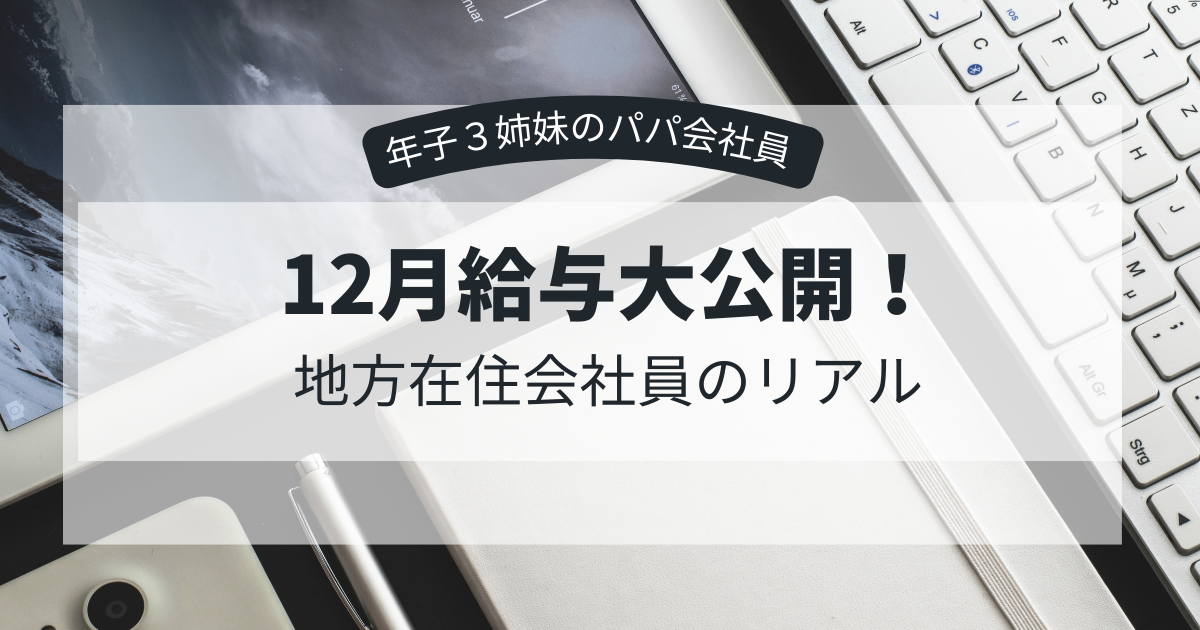
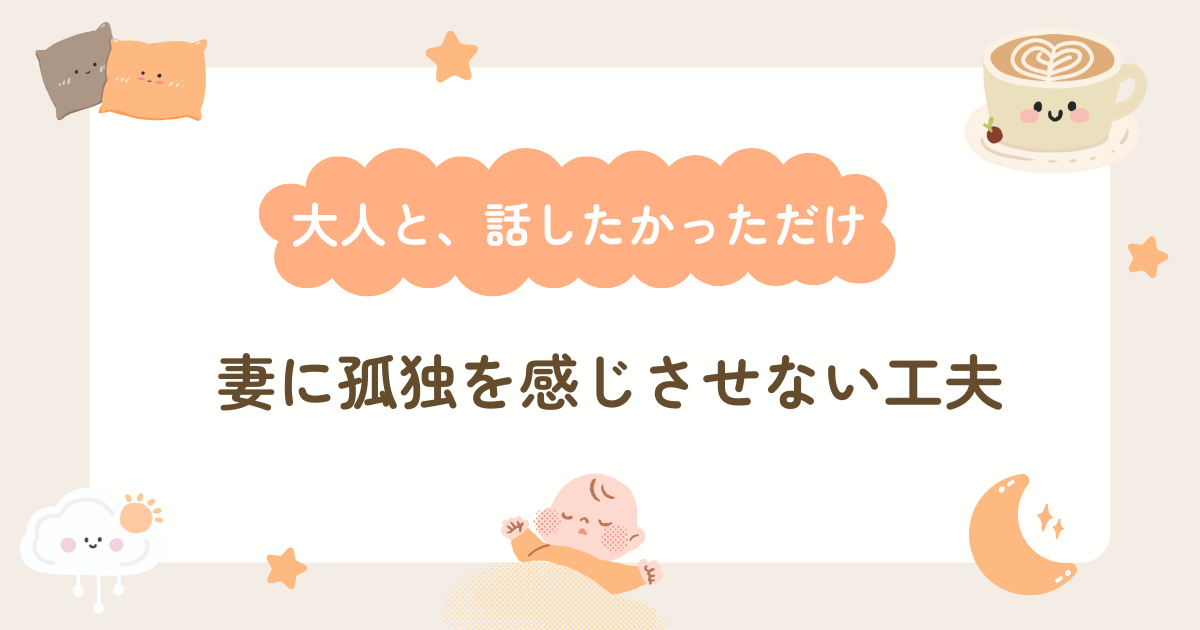

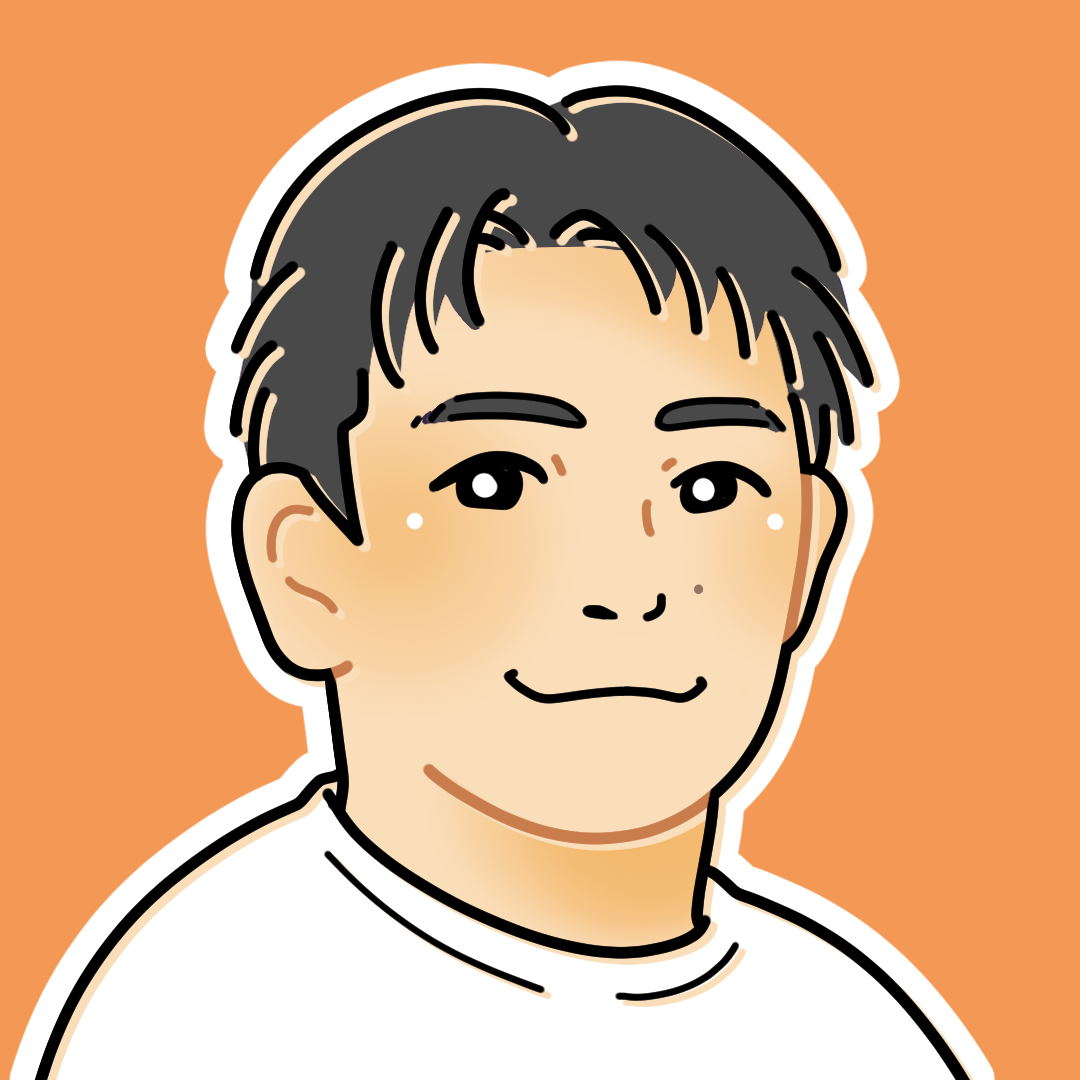
コメント