
はじめに:143%の正体
年利143%!?
…ではありません。
これは返戻率(へんれいりつ)=払った総額に対する戻り額の割合。
40年かけてやっと1.43倍になるだけで、年利に直すと1%台です。
もしこの数字に「お得そう」と思ってしまったなら要注意。
広告の数字マジックに反応する人は、ポンジスキーム的な仕組みにも騙されやすい傾向があります。
返戻率(戻り率)とは?
計算式はシンプル。
返戻率=(解約返戻金 ÷ 払込総額) × 100
時間の概念がない総額比なので、実態以上に“増えた感”が出やすい数字です。
例えるなら、1リットルの水を「1000mlあります!」と言っているようなもの。
年利や利回りとは全く別物です。
インフレで減る実質価値
インフレ率2%で40年後の物価は約2.2倍。
額面516万円の価値は、現在価値で約235万円にまで減少します。
たとえば1984年に380円だった牛丼は今では500円前後。
40年前の100万円は今の感覚で45万円程度の価値しかありません。
名目 vs 実質(インフレ2%想定)
| 比較表 | 名目額 | 実質価値 |
|---|---|---|
| 返戻率143%の保険 | 516万円 | 約235万円 |
| NISA(オルカン5%) | 1,507万円 | 約870万円 |
| 銀行定期預金(年利0.002%) | 504万円 | 約229万円 |
ポンジスキームとは?
名前の由来は、1920年代の米国で投資家を騙した詐欺師チャールズ・ポンジ。
彼は「45日で40%の利益」をうたい、郵便切手の国際クーポンを使った投資を装いました。
当時のボストンには、配当を受け取った人たちが友人や親戚を連れて列を作り、ポンジの事務所の前には日々群衆が押し寄せました。
しかし実態は全く投資しておらず、新しい参加者の資金で古い参加者へ配当を払うだけ。わずか数カ月で破綻し、多くの人が財産を失いました。
現代でも、この“新しいお金で古い約束を守る”構造は形を変えて残っています。
保険はもちろん合法ですが、多くの加入者の掛け金で一部に給付、残りは利益という構造は似ています。
なぜ1920年の手法が現代でも通用するのか
理由はシンプル。人間の心理は100年経っても変わらないからです。
- 短期間で高利回りという言葉に弱い
- 数字だけを見て仕組みやリスクを確認しない
- 周囲がやっていると自分も飛び込む(同調バイアス)
心理的な落とし穴
さらに現代にはもう一つの要因があります。
「新NISAは怖いけど、保険は安心」という心理です。
新しい投資はやり方やリスクがわからず不安。でも保険は契約や窓口説明があり「守り」のイメージが強い。
そこに「資産形成もできる」「143%戻る」という“安心+お得”セットを提示されると、投資初心者は飛びつきやすくなります。
どうすればいいのか?
- 数字を「年利換算」してみる
- インフレ率を考慮して実質価値を計算する
- 比較対象(NISA・投資信託・定期預金など)と並べて見る
- 商品の仕組みやお金の流れを理解してから契約する
特に長期の資産形成では、複利効果のある運用商品と、必要に応じた最低限の保険を組み合わせるのが現実的です。
まとめ
注意喚起
・返戻率143%は年利1%台の総額比
・インフレで実質価値は半分以下
・数字マジックは100年前の手法と同じく心理を突く
・安心感とお得感のコンボは強力、だが冷静な計算が必要
・「どうすればいいか」まで考えて判断する

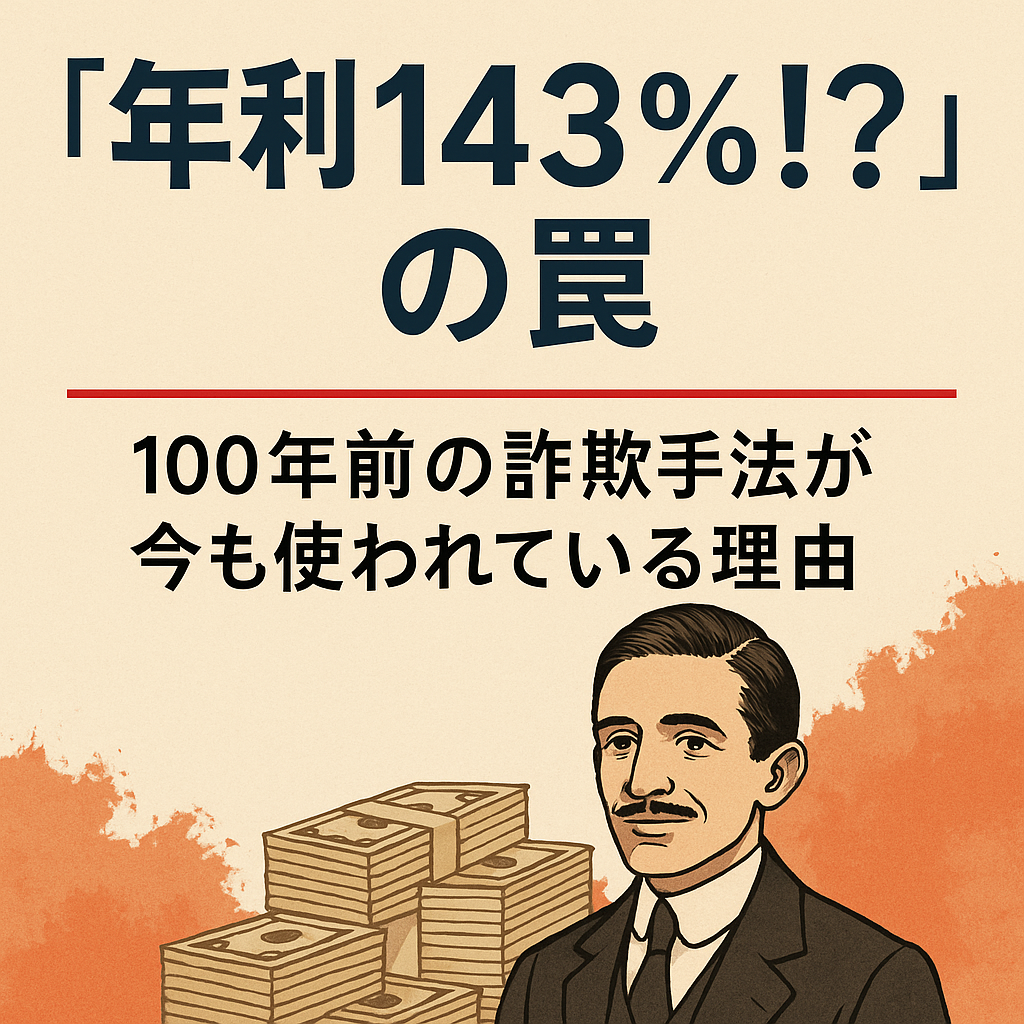
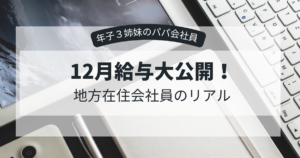
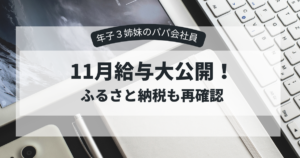


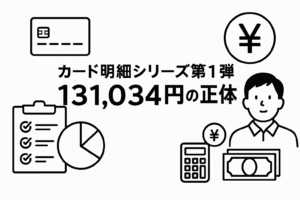
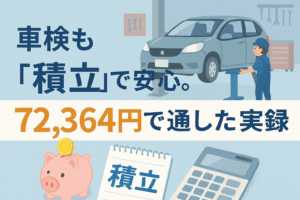
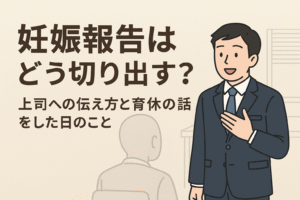
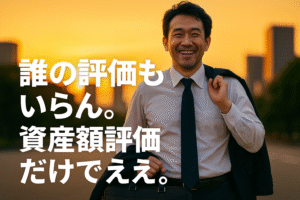



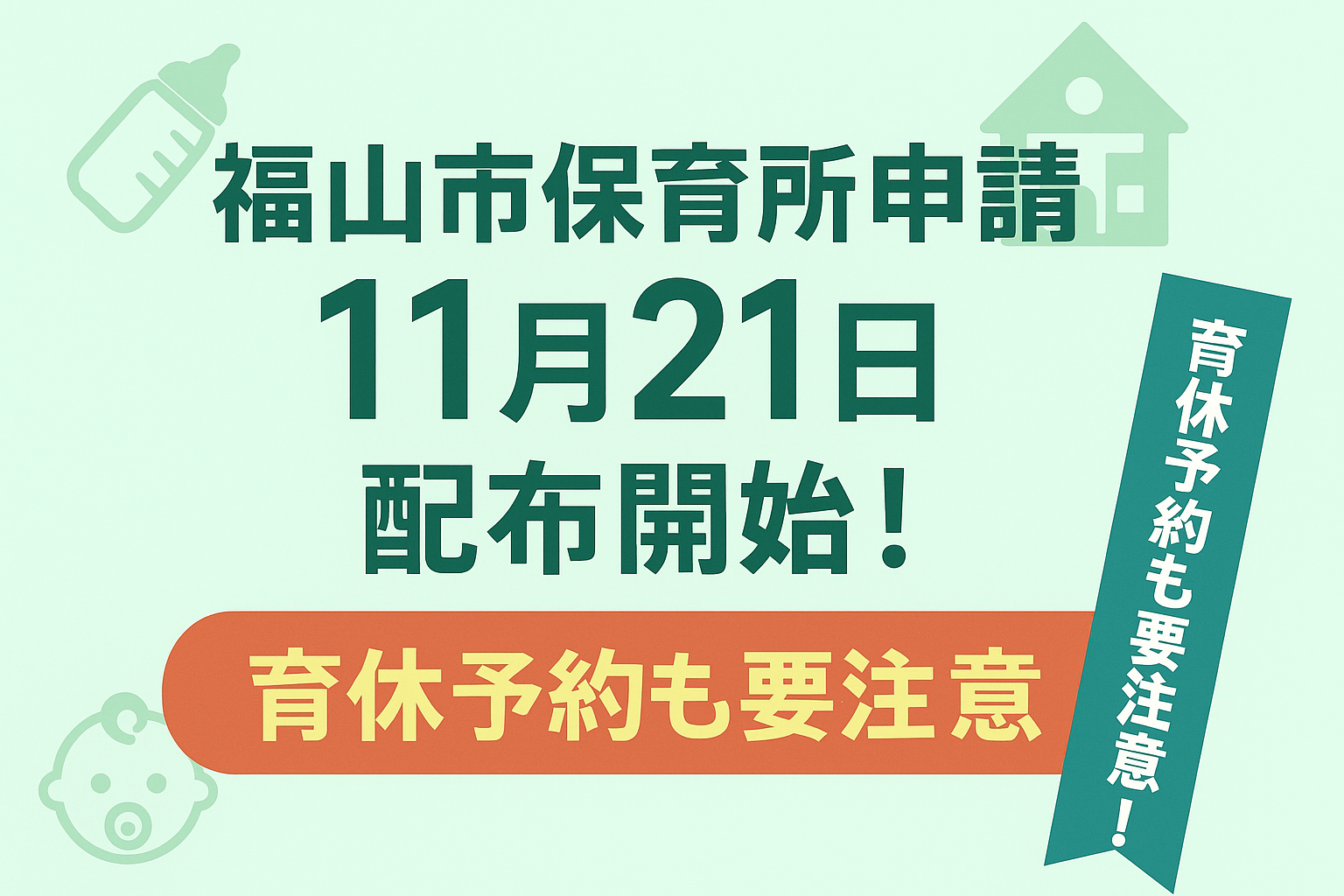

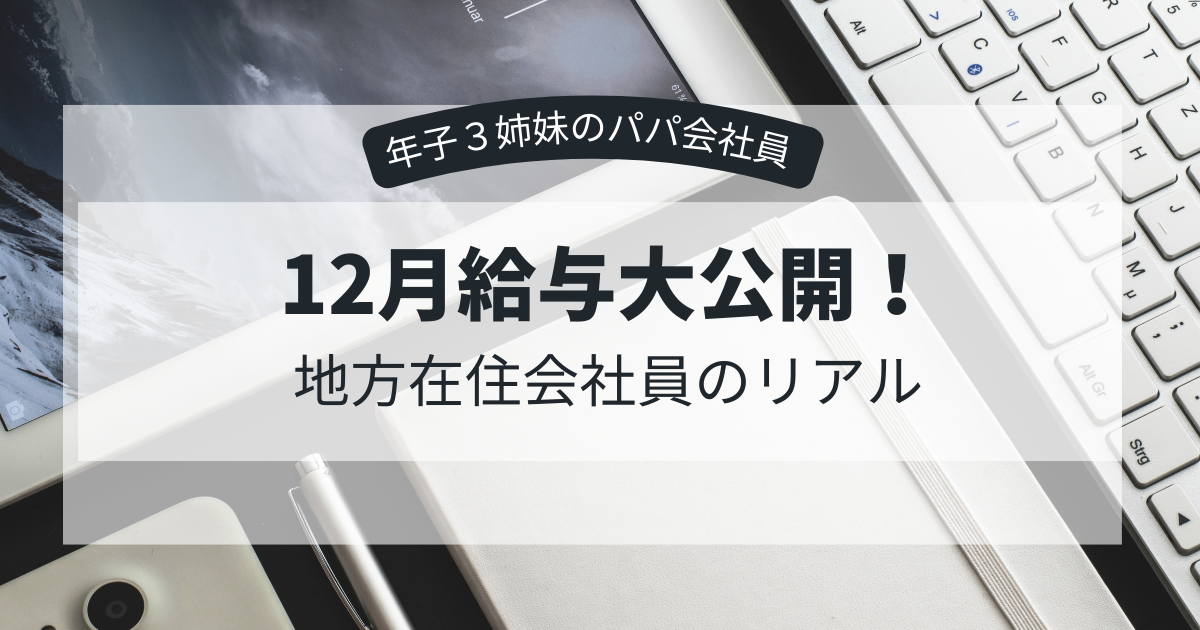
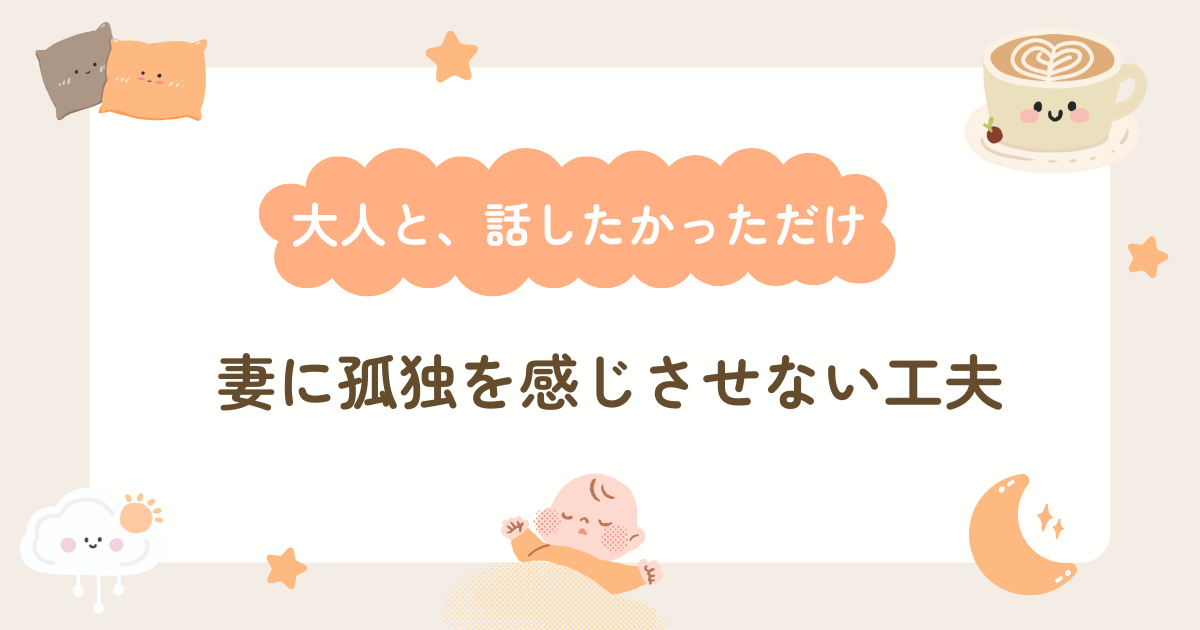


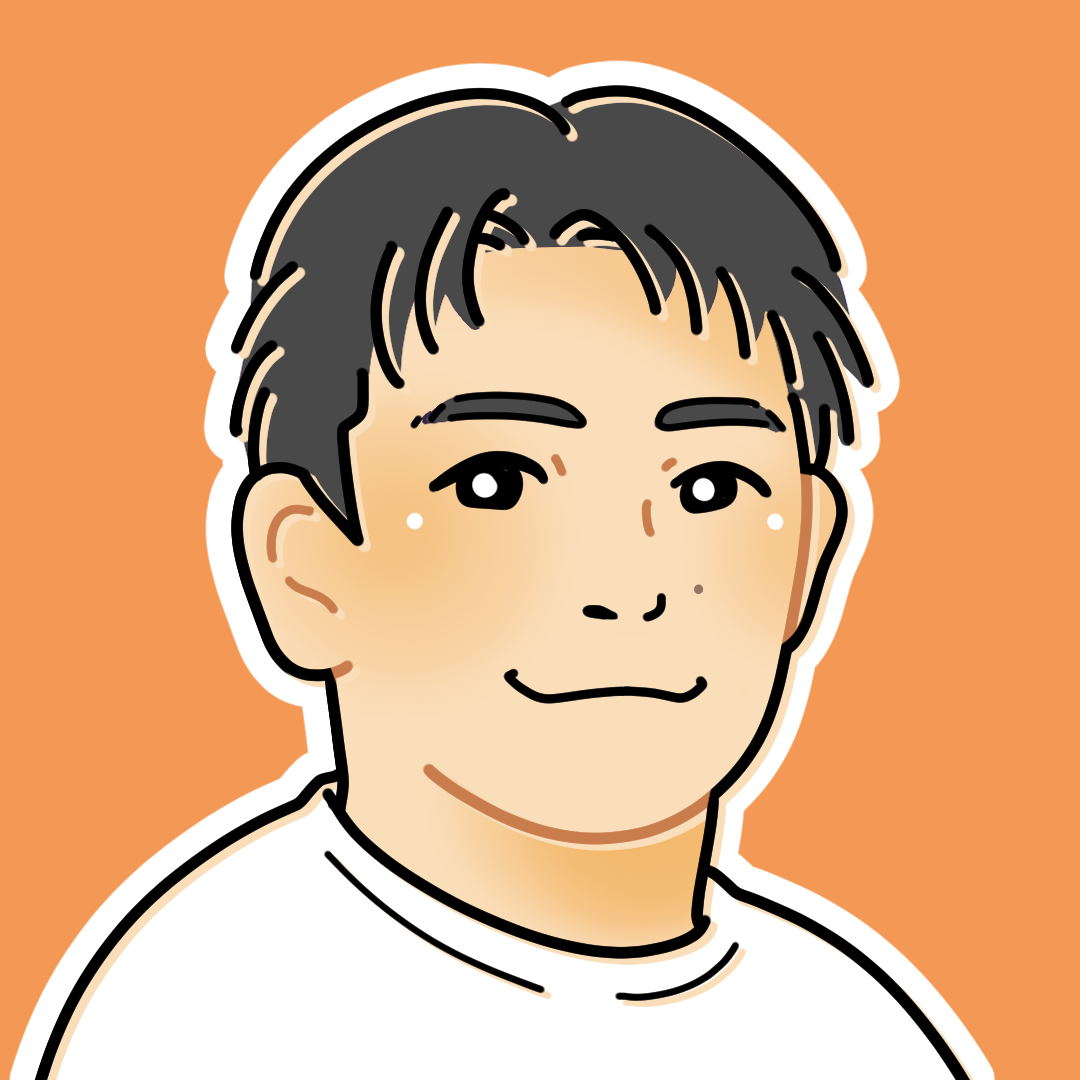
コメント