【はじめに】教育費、どうやって準備する?
子育てをしていると、一度はぶつかる悩み──
「大学の費用って、どうやって準備するの?」
我が家には1歳と0歳の子どもがいます。
保育園や習い事、病院代…何かと出費が続く中で、将来の教育費も視野に入れなければと思い始めました。
そこで我が家が選んだのは、
児童手当をそのまま投資にまわす
という方法です。
【児童手当を毎月つみたてNISAで投資】
児童手当は現在、毎月15,000円(1人目)を受給中。
これをそのままつみたてNISAのインデックスファンドに投資しています。
投資目的はズバリ、大学進学時の費用。
入学金・授業料・引っ越し費用など、進学時にはまとまったお金が必要になります。
高校までは貯金や日々の家計でなんとかし、大学入学時に備える設計にしています。
【積立シミュレーション:どれくらい貯まる?】
仮に0歳から15年間、児童手当を毎月15,000円ずつ積立てたとします。
- 積立額合計(元本):15,000円 × 12ヶ月 × 15年 = 2,700,000円
- 年利5%で運用した場合:約4,450,000円
これは入学金・初年度学費・一人暮らし準備まで含めた「進学資金」としてかなり心強い額です。
【でも…18歳の時に暴落が来たら?】
よく聞かれるのが「そのとき株価が暴落していたらどうするの?」という不安。
確かに、受験の年に大きな下落が起きていれば、運用資産が減ってしまい、
「必要なときにお金が足りない」という事態になりかねません。
そこで我が家では、もう1つの手段を用意しています。
【そのときは奨学金を活用する】
暴落時に無理に資産を取り崩さないために、我が家では奨学金を活用する方針をとっています。
「奨学金=借金でしょ?」というイメージがあるかもしれませんが、日本の奨学金(特に第一種)は、
- 利子なし(無利子)
- 卒業後からゆっくり返済
- 在学中は返済不要
- 一定の年収以下で返済猶予制度もあり
というかなり優遇された制度なんです。
つまり、「今すぐ現金が必要」な時にお金を借りて、
投資資産はそのまま残す or 回復を待つという戦略が取れます。
【戦略的に使う:奨学金 × 投資】
我が家の考え方はこうです👇
- 児童手当を長期投資で育てる
- 18歳時に暴落があれば、奨学金で“時間を買う”
- 4年間の大学生活中に回復が見込めれば、資産を取り崩さず済む
- 奨学金の返済も、投資の運用益からゆるやかに対応
これによって、暴落に備えながらも、リターンを最大化できる資金設計になります。
【補足:学資保険は“インフレに負ける”】
教育費の準備といえば、「学資保険」が定番です。
返戻率105%程度の商品もありますが、長期で見るとインフレに勝てないという問題があります。
たとえば、2007年から2025年までの18年間で、日本の物価は約10%以上上昇しています(CPIベース)。
つまり、当時の1万円の価値は、今や9,000円台。
仮に15年間、毎月15,000円を積み立てて:
- 学資保険(返戻率105%):約3,400,000円
- 年利5%の投資:約4,450,000円
実質価値(インフレ調整後)では、学資保険のほうが目減りする可能性が高いのです。
【教育費準備、どう考える?】
いろんな選択肢がある中で、我が家は以下の理由から投資を選びました:
- 学資保険よりもリターンの期待値が高い
- 奨学金を組み合わせれば、暴落対策も可能
- 手元の現金は今必要な育児費用に使える
- 将来、子どもにお金の話をオープンにできるきっかけにもなる
【まとめ:お金は「今」か「未来」かの分配】
教育費は人生の中でも大きな支出です。
でも「今すぐ現金で確保しておく」か、「未来に増やす設計をする」かは家庭ごとの考え方でOK。
わが家は、「今を大切にしながら、未来にそなえる」ために
児童手当×投資×奨学金という組み合わせを選びました。
将来、子どもがどんな進路を選ぶとしても、
お金のことで選択肢が狭まらないように──そんな願いを込めて、今日もコツコツ積み立てを続けています。


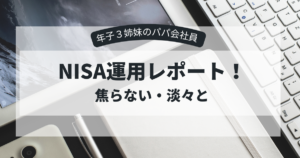
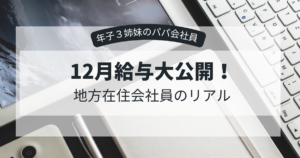
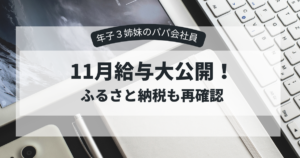


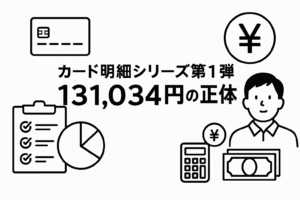
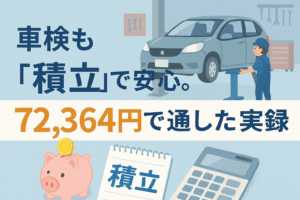
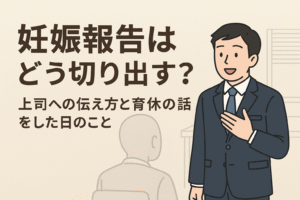



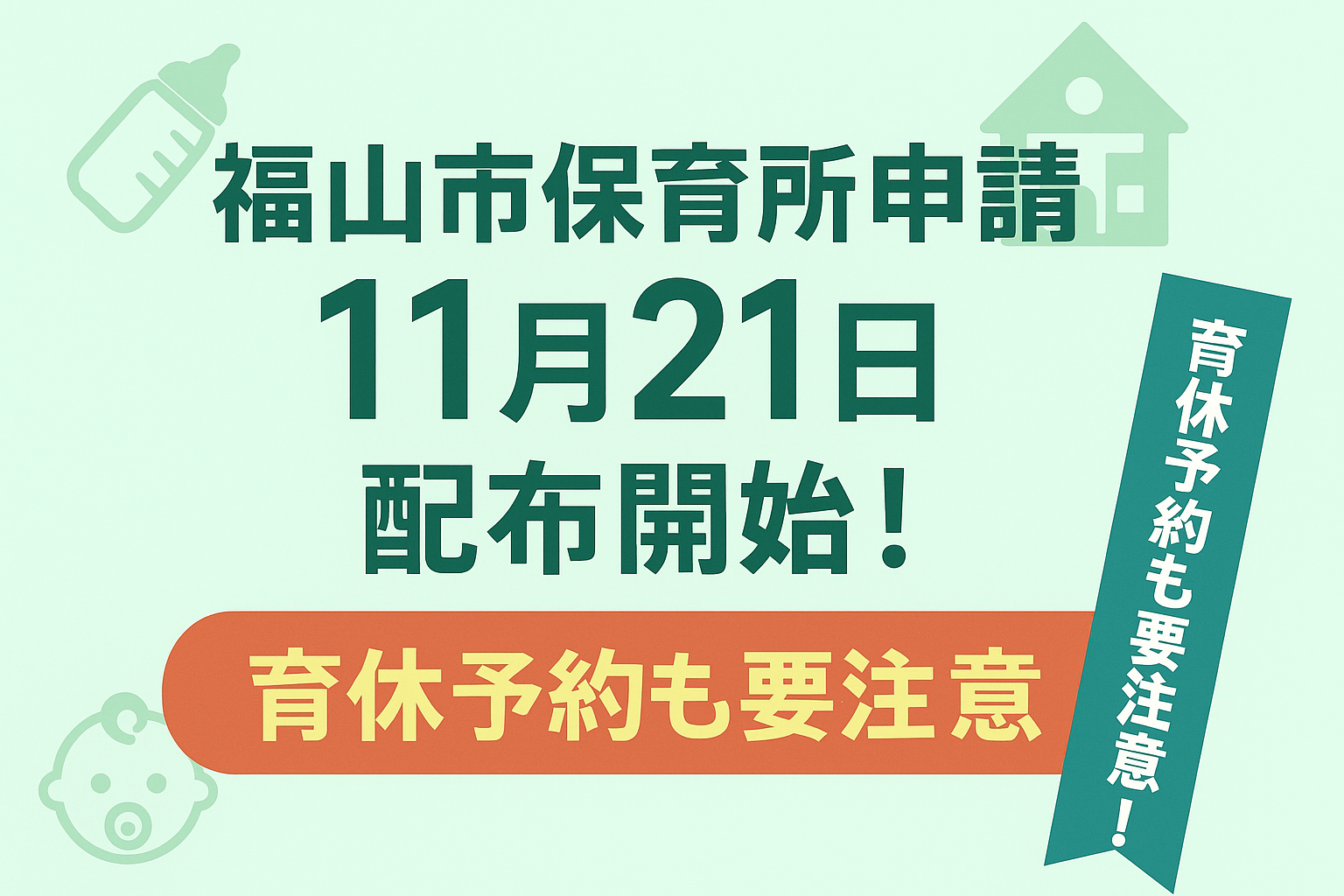
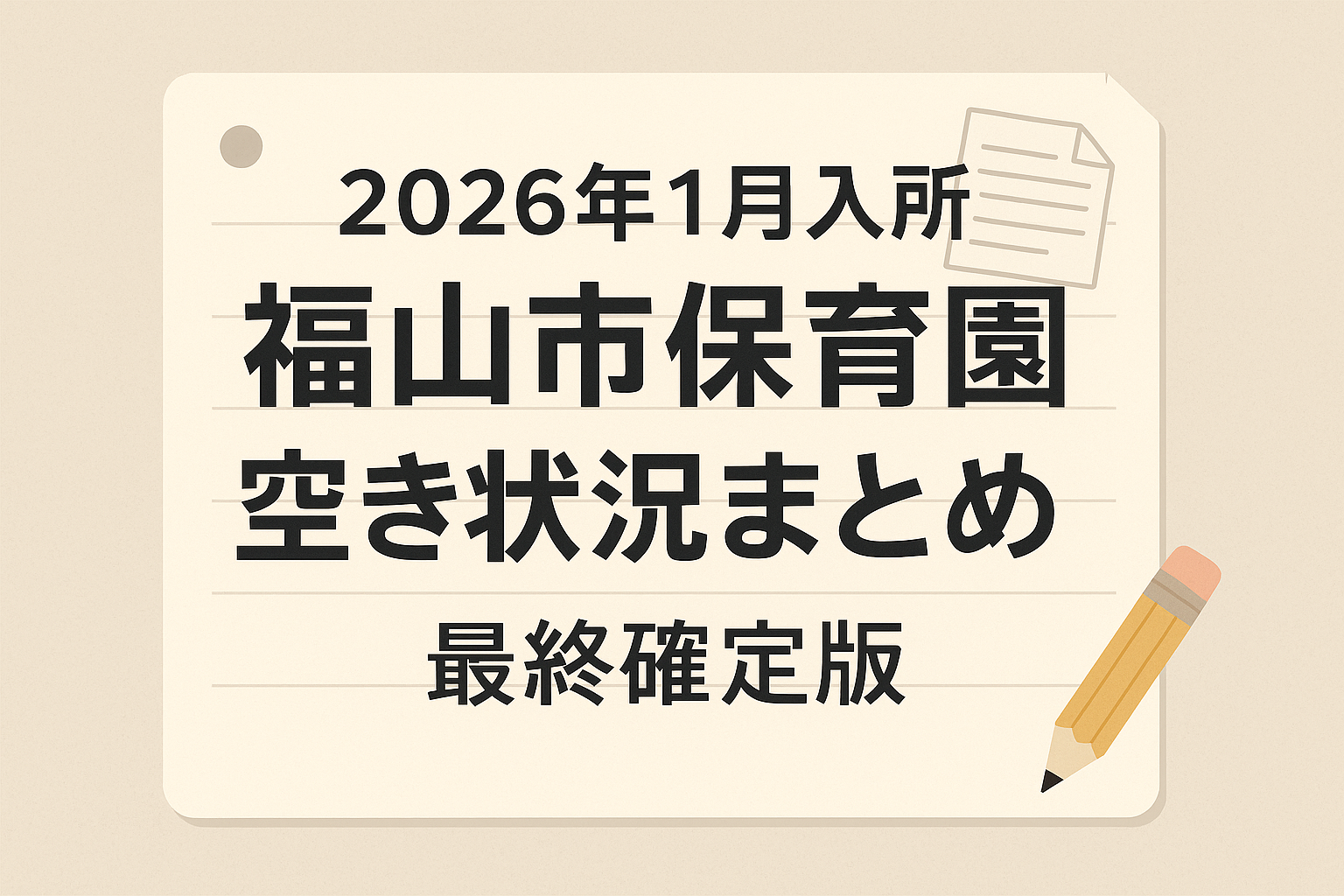
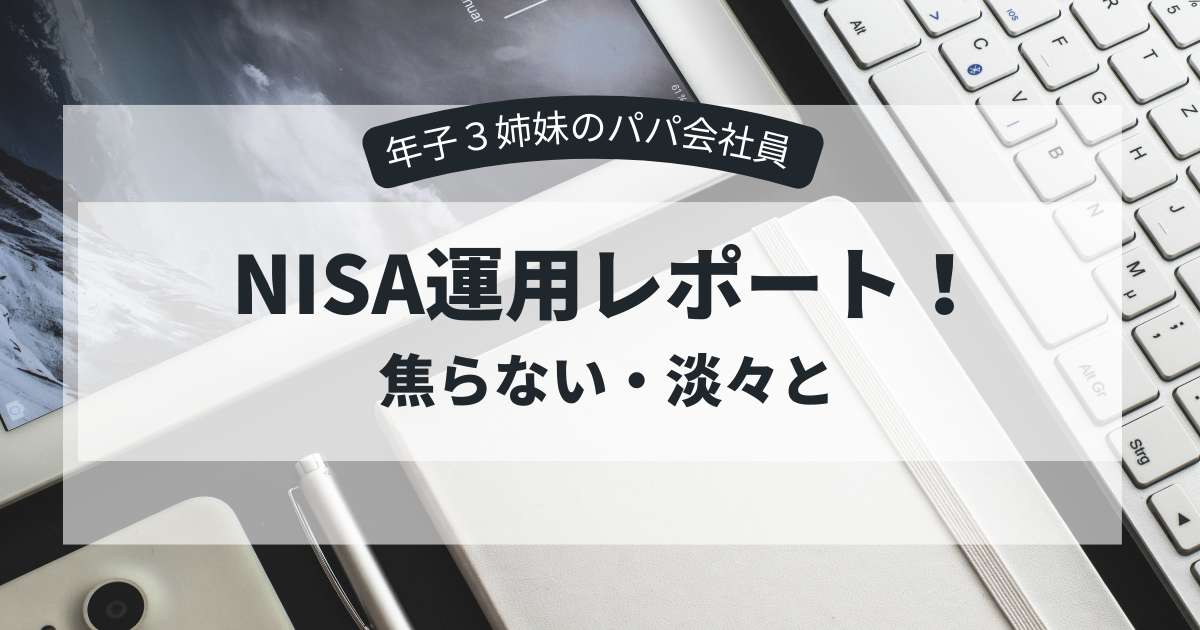
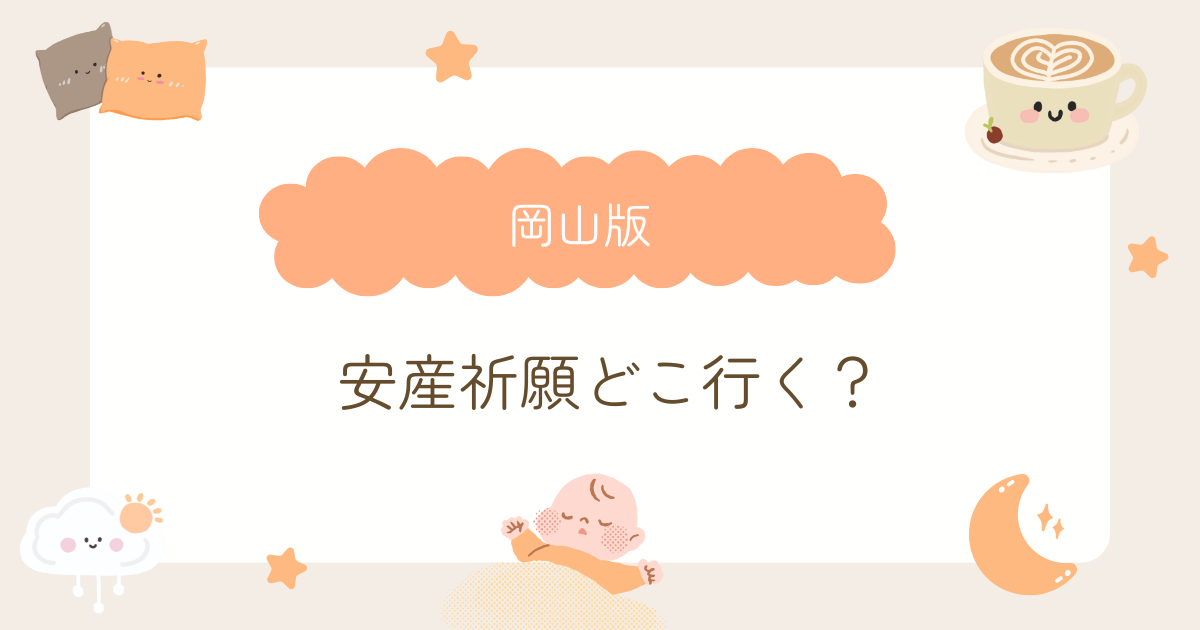
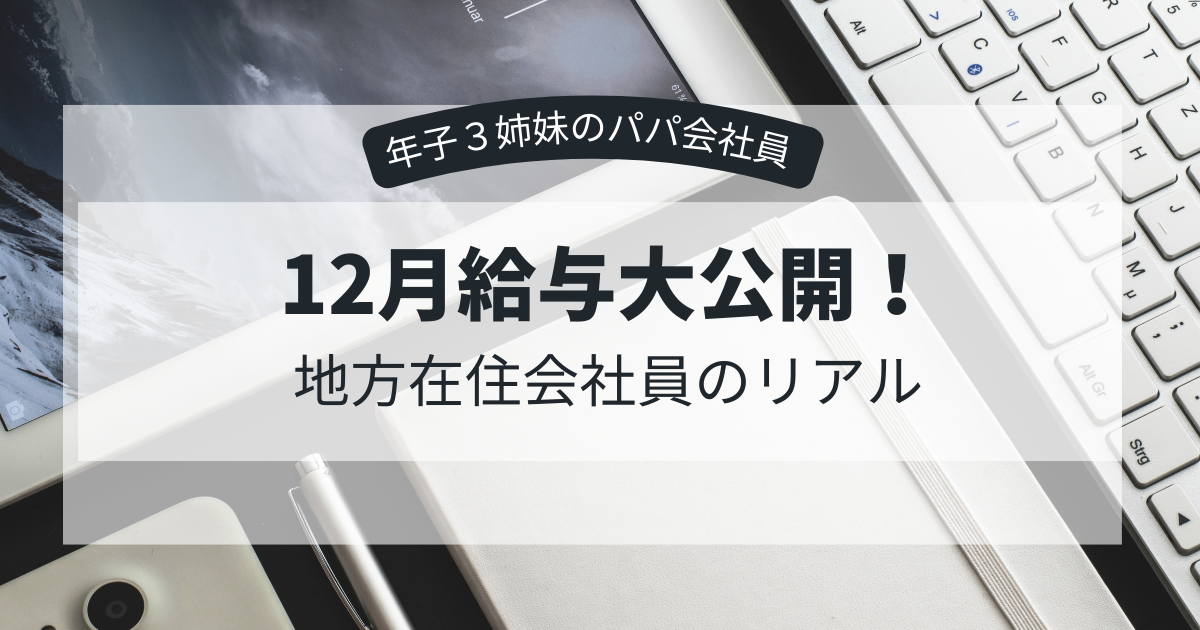
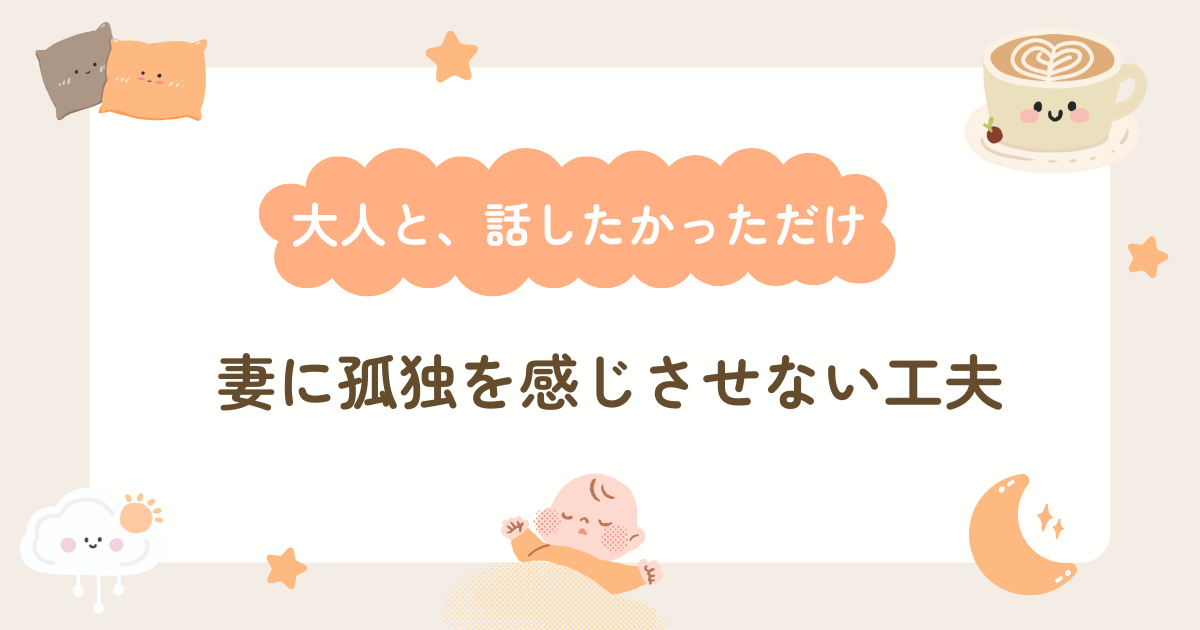

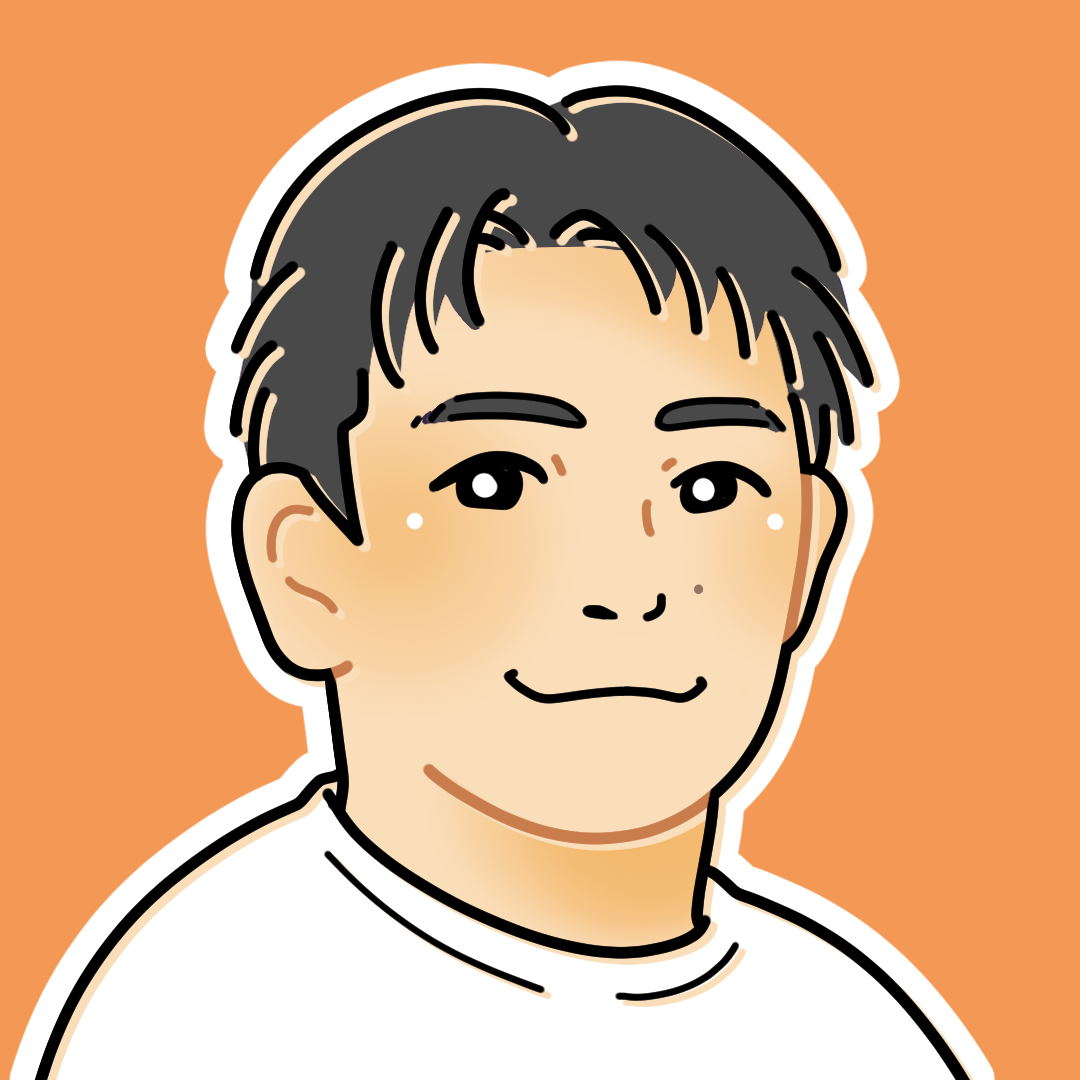
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 👉 児童手当×つみたてNISAで教育資金を準備!我が家の戦略を公開 […]