【育休復帰する人向け】手取りを賢く守る!知っておくべき2つの重要制度と手続き
育児休業から復帰される皆様、職場への復帰おめでとうございます!仕事と育児の両立に向けて、本記事では、育休復帰後の手取り額を維持し、将来の年金も確保するために知っておくべき2つの重要な制度を、手続きと合わせて解説します。賢く制度を活用し、安心して職場に戻りましょう。
知っておきたい!育休復帰後の手取りと年金の関係
育休復帰後の働き方の変化は、給与、そして手取り額に影響を与える可能性があります。しかし、適切な制度を利用することで、手取りの減少を抑え、将来の年金も守ることができます。
活用すべき2つの重要制度
- 育児休業等終了時報酬月額変更届:復帰後の給与で社会保険料を再計算し、手取りを増やす可能性。
- 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置:時短勤務でも将来の年金が減らないようにするための制度。
1. 育児休業等終了時報酬月額変更届
制度概要: 育休復帰後の給与が大きく変動した場合、申し出により社会保険料を新しい給与に合わせて再計算できる制度。手取りが増える可能性があります。
申請条件: 育児休業を終了し、復帰後の標準報酬月額が育休前と比較して2等級以上変動した場合。
申請方法: 会社に申し出て、会社経由で年金事務所に届け出。原則として添付書類は不要です。
2. 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
制度概要: 3歳未満の子を養育し、時短勤務などで給与が下がった場合でも、将来の年金計算は育休前の標準報酬月額に基づいて行われる制度。
申請条件: 3歳未満の子を養育しており、育休前と比べて標準報酬月額が下がっていること(1等級でも該当)。
申請方法: 会社に申し出て、子の戸籍謄本または戸籍抄本と自身の住民票の写しを添えて、会社経由で年金事務所に届け出。
手続きの流れと注意点
- 会社への相談: 育休からの復帰が決まったら、まずは人事・労務担当者にこれらの制度について相談しましょう。申請の意思を伝え、必要な書類や手続きの流れを確認します。
- 必要書類の準備: 「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」には、お子様の戸籍謄本(または抄本)とご自身の住民票の写しが必要です。早めに準備しておくとスムーズです。
- 申請書の提出: 会社の指示に従い、必要な書類とともに申請書を提出します。
- 会社の対応: 会社が年金事務所へ手続きを行います。
- 注意点:
- 申請にはご本人の意思確認が必要です。
- 復帰後翌年9月までに次の出産予定がある場合や傷病手当金を使う予定がある場合は、申請しない方が有利なこともあります。該当する場合は、会社や年金事務所に相談しましょう。
- どちらの制度も、条件に該当するかどうか自分で判断できない場合でも、とりあえず申請してみることをお勧めします。該当する場合のみ措置が実施され、不利益はありません。
- 遡って申請できる場合がありますが、早めの手続きが安心です。
まずは一歩!会社への相談から始めましょう
育休からの復帰は、新しい生活のスタートです。これらの制度を理解し、活用することで、経済的な不安を軽減し、仕事と育児の両立をより安心して送ることができます。まずは、勤務先の人事・労務担当者に相談することから始めてみましょう。
【追記】文字が多くてよくわからなかったパパママへ:1才の赤ちゃんでもわかる(かもしれない)お話
魔法1:【お給料へんしん!】のお話
パパやママのお仕事のお給料が、前よりちょっとだけ少なくなったら、払うお金(ほけんりょう)も少なくなる魔法。使えるお金が少し増えるかも!
魔法2:【未来のお金まもり!】のお話
大きくなった時にもらえる大事なお金(ねんきん)が、お給料が少なくても、前と同じように貯まっていく魔法。
わからないことは、会社の優しい人に聞いてみてね!
まとめ
育休復帰後の手取りを賢く守り、将来の年金もしっかり確保するためには、「育児休業等終了時報酬月額変更届」と「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」の2つの制度が非常に重要です。ご自身の状況に合わせてこれらの制度を活用することで、経済的な負担を軽減し、安心して仕事と育児の両立を送ることができます。まずは、ためらわずに会社の人事・労務担当者に相談し、手続きを進めていきましょう。


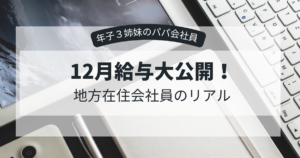
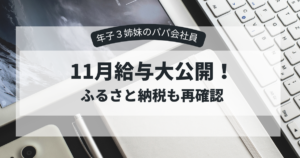


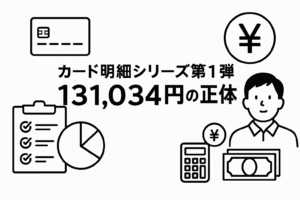
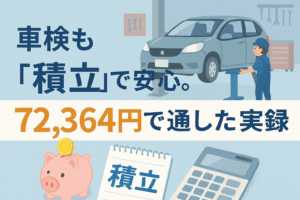
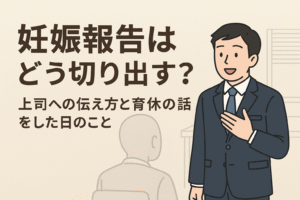
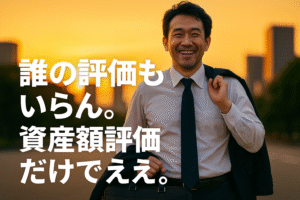



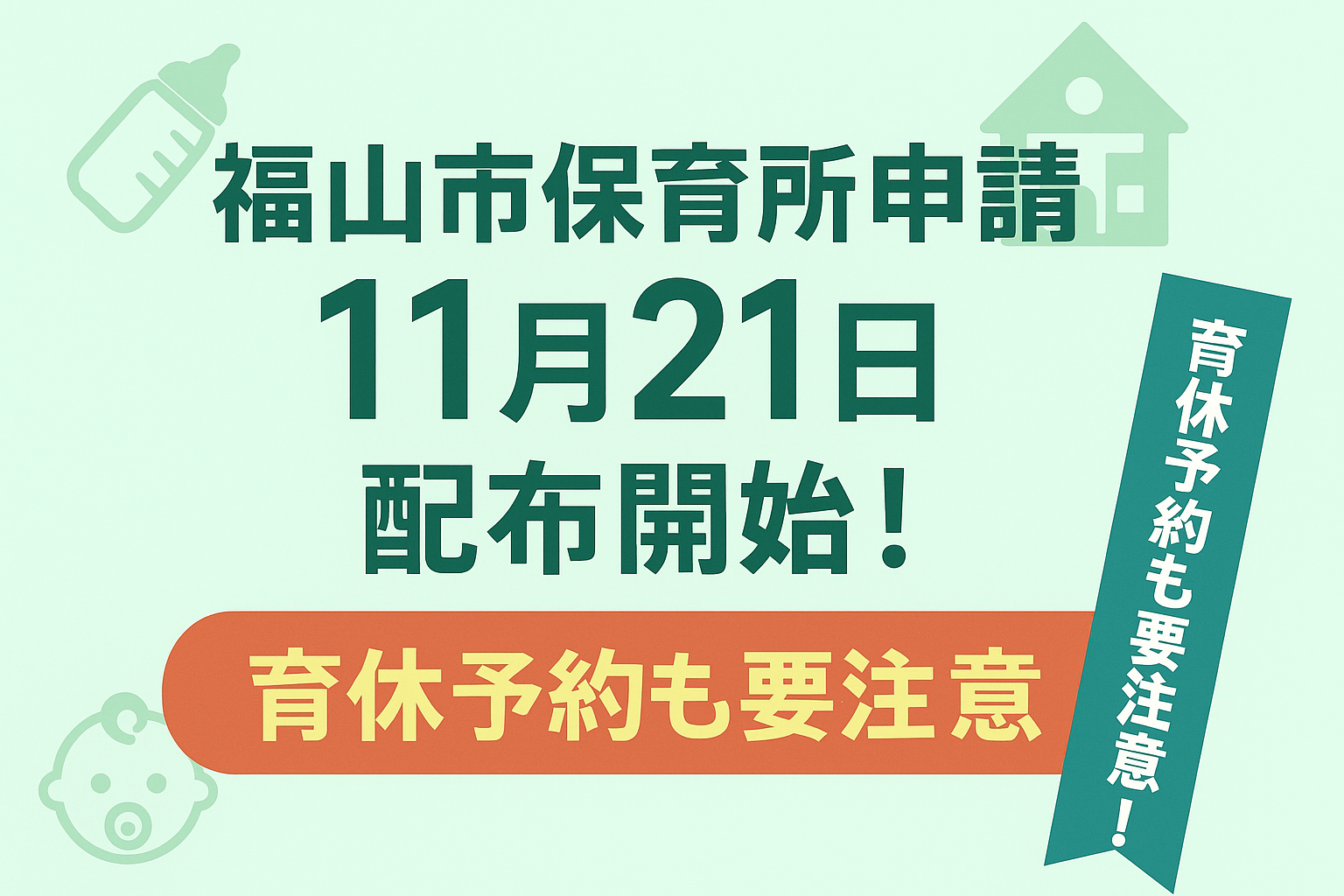

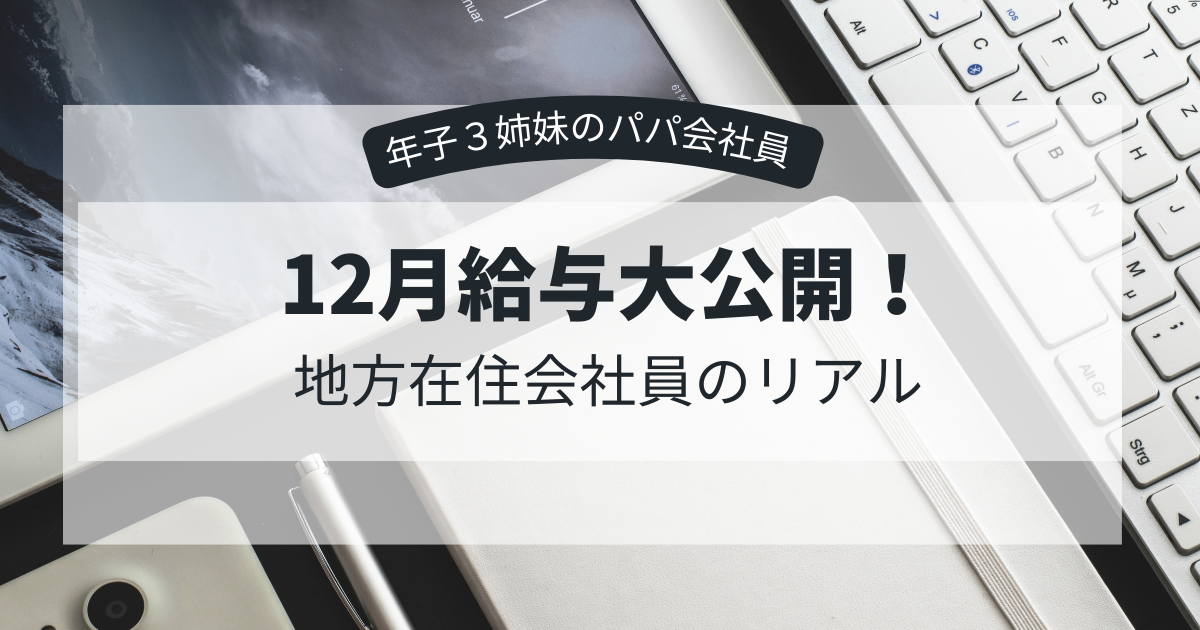
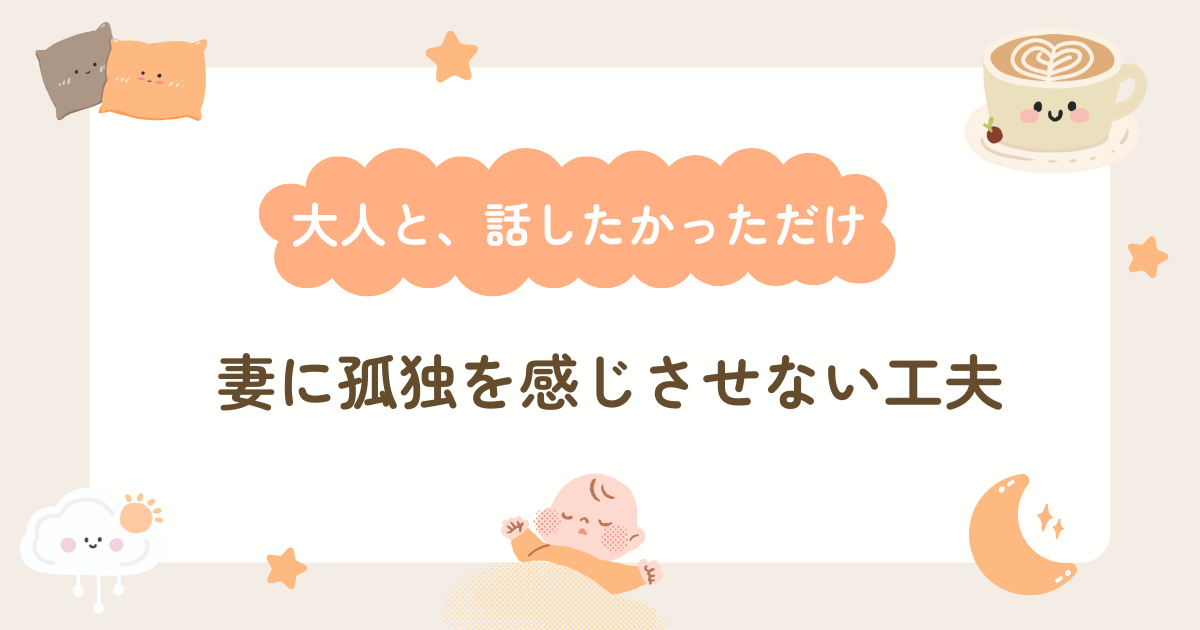


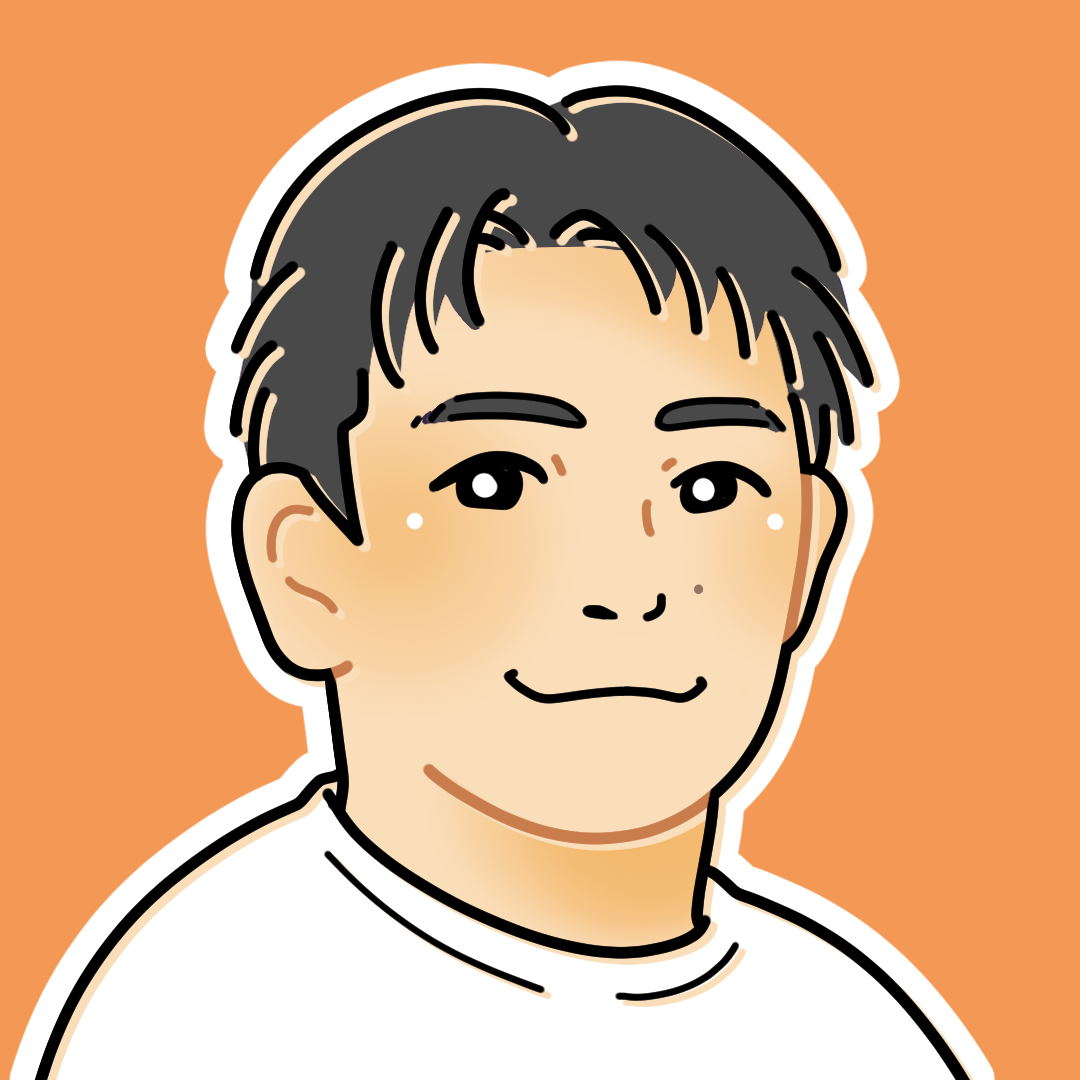
コメント